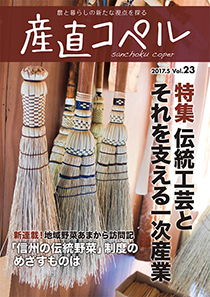全国の地域おこしの先進事例が満載 ―産直コペルより―
農家を訪ねて vol.5 命が育つお手伝い 有機農業の土作り
長野市中条村御山里地区で有機農業を営む有限会社まごころ・ふれあい農園の代表久保田清隆(52)さん。
中条村は標高虫倉山の中腹にあり、標高は750m、棚田と北アルプスの景観が美しい地域だ。しかし、傾斜地が多く農業適地とは言えない。久保田さんはその中条村で約4ha、年間100品目以上の野菜を栽培している。個人への直販を中心にレストランとの契約栽培や委託での栽培も行なう。
研修生も多く受け入れており、農業技術の伝承にも力を入れている。県の農業アドバイザーも務める
土着菌による土作り
久保田さんの有機農業の核心は、土着菌を培養する土作りだ。
「土着菌を培養して、畑に微生物を増やしてあげることで、免疫力の高い作物が育ち病気にも強くなります」という。
土着菌の培養方法は、シンプルだ。まず、野山の草を刈ってきて、黒砂糖と一緒に漬物樽に入れるというもの。「微生物は、糖が好きなので、細かく砕いた黒砂糖で培養出来る」と話す。しばらく漬け込むと底に液が溜まる。この液の中には大量の微生物がいるのだ。この液と籾殻、米ぬかを混ぜて畑にまいていく。これが、久保田さんの土作りだ。
使う肥料は鶏糞肥料だけ。「肥料も少量しか使わない。微生物が食べられる分だけあげる。有機物を微生物が分解して、無機物にし、作物が栄養として吸収する。有機物が多すぎると、分解されずに土に残ってしまう。これが病気などの原因になる」と語る。
「栄養をあげすぎている事が様々な病気の原因だと思う。僕は作物の生命力を少し手助けするだけ」。土を作り、少し手をかけるだけで、必ず作物は育つ。
ナスやトマトなど連作障害の代表品種も問題なく作り続けられる。久保田さんのこの野菜を求めて、多くの人が久保田さんのもとを訪れているのだ。
有機農業との出会いは奥さんとの出会い
久保田さんの有機農業との出会いは、イコール奥さんとの出会いだった。奥さんと結婚し、「家庭菜園で美味しい野菜を作るから」と話すと、「私は有機野菜にしか興味がないから、有機で作ってね」と言われた。
久保田さんは、農業大学校を卒業後、種苗会社で働いていた。農家に農業を指導する立場だ。プロとしての自負がある。「有機農業なんて絶対に無理だ」と口論になったが、奥さんは全く引かなかった。久保田さんが渋々折れ、有機栽培を始める事になった。
「虫だらけになるし、いいものは作れないだろうけど、覚悟しておけよ」と奥さんには言ったが、何とか良い物を作ろうと努力した。
病気にはなるし虫もつく。頭の中には殺菌剤や殺虫剤の名前が浮かぶ。しかし、その言葉を打ち消しながら農薬を使わない方法を調べて回った。酢や牛乳をかけたり、病気の葉をちぎったり、良いと思われる事はなんでもやった。それでもどうにもならない。枯れてしまう野菜を見守るしかなかった。
しばらくして、病気や虫食いになってから、対応していては遅いのではないか、と感じるようになってきた。
「病気にならない作物を作らなくてはいけない」。技術員としての自分は、「病気や害虫をみて、いかにそれを叩き、いかに大きく育てるか」、しか考えていなかった。そのことに気がついてからは、大切なのは、「野菜自身の健康だ」と考えるようになった。「医者の目から親の目になったんだね」と笑う。
なぜ虫がつくのか、なぜ病気になるのか、を考えた。今まで見過ごしていただけで、自然界は、メッセージを出しているということに気が付いた。失敗を繰り返しながら、辿り着いたのが、現在の土作りだった。
農業への葛藤の日々
久保田さんは、37歳のときに脱サラして専業農家になった。
「これしか道がないと思った」と久保田さんは語る。
久保田さんは、25歳のときから有機農業を続け、3年が経つ頃には、土作りのコツも掴み、美味しい健康な野菜が収穫出来る様になっていた。しかし、「農業では、一家4人を養う事は出来ない。仕事を辞めて農業をやることはないだろう」と考えていた。
しかし、日に日に農業への思いは募る。一番苦しかったのは「現実と理想のギャップかもしれない」と話す。仕事では、農薬や化学肥料の使い方を指導し、家に帰れば、農薬や化学肥料を使わずに健康な作物が育っている、ということへの違和感が大きくなっていった。
自分たちの家族は、健康な野菜を食べて風邪も引かずに元気に暮らしている。「自分の家族だけ守ればそれでいいのか」、という思いが立ち上がってきた。
我慢が出来なくなった久保田さんは奥さんに打ち明けた。「農業でやっていきたいんだ。でも、家族を養えるかは、分からない」。奥さんは、「いつ言い出すかと思っていたわ」と受け入れてくれた。
子どもたちにも「もしかしたらこの家を手放さなくちゃいけなくなるかもしれない」と相談すると、当時小学6年生だった長女は、「私はテント生活でもいいよ!」笑った。小学2年生の長男も「僕はお父さんとお母さんがいるなら、穴掘って暮らす〜」と言ってくれた。
子どもたちの言葉に救われた。
奥さんも、「家族は、私が看護師を続けながら何とかする」と約束してくれた、と久保田さんは嬉しそうに話す。しかし、1年も経たない内に、「あなただけ農業するのはずるい。私もやる」と奥さんも仕事を辞めることになる。
「えぇー本当かよ!という気持ちでした。家のローンもまだまだ残っていましたから」と笑う。
ただ、もうやるしかない、前進するしかないという強い気持ちになった。
一般の流通には乗せられない 別の流通を模索
仕事を辞めて迎えた就農1年目。手始めに、兼業時代に作っていたジャガイモの販売を試みた。
長野市内のレストランを周り、10キログラムあたり2000円で買ってもらえないかと営業に回った。しかし、ほとんど相手にされなかった。「それぞれ仲買業者さんや農家さんと契約していて、いきなりいったって相手にされないと分かるけれど、当時は、それも分からなかった」と振り返る。
3日程回っていると、八百屋さんが「お兄ちゃん頑張っているね。知り合いの市場を紹介してあげるから、その野菜の相場を調べてみなよ」といわれ、市場に行った。
そこで言われた言葉が衝撃的だった。「これなら、10キログラムで100円〜200円くらいだね」。「有機で作ったんです!」と食い下がったが、「有機だろうと、この大きさなら100円だな、こっちは少し大きいから、200円」。
自分が一生懸命作ったジャガイモが、10キログラム一箱で100円〜200円にしかならないのか、と落胆した。それと同時に、自分の野菜は普通の流通には、のせられないと知った。
食べても貰えず、100円という値段をつけられたことが悔しかった。100円で売るくらいなら、食べてもらいたい、と考えた久保田さんは、レストランや知り合いに今度は、配り歩いた。
効果はてきめんだった。
「こんな美味しい野菜が作れるのか、他にはどんなものをつくっているの」という問い合わせが来た。更に、コープ長野からは、「コーナーを作るから置いて販売してみないか」という話しもきた。久保田さんは喜んで引き受けた。まだ直売所も数える程の時代だ。
持って行けば、すぐに売れた。「面白い様に売れましたね。これは、なんとかなる!と思った瞬間でした」と笑う。
その売れ行きを見て、最初は、置き野菜で手数料無しで良いよと言っていたコープ長野にも、「やはり手数料を…」と言われ、最初は10%、次は15%、20%と言う具合に徐々に上がっていった。
長野市内向けに宅配サービスも始めた。「田舎じゃ、みんな周りに農地があるのに、だれがそんなものを買うんだ」という人もいた。しかし、始めてみると、県外から有機野菜を取っている人たちからの注文が相次いだ。1年目で60件の会員が集まった。1年目で600万を売り上げた。
仙人農業ではなく、オープンな農業へ
「本当に大変だったのは周りの反応」と久保田さん。平成10年当時、有機農業へのイメージはまだまだ変わり者の農業だった。
兼業農家をしていた両親は大反対。「俺の年金で、お前たちを食わせなくちゃいけないのか。先祖からもらった土地を駄目にするのか!」と父親は怒鳴り、母親は泣いていた。奥さんが農業をすると言った時には、奥さんの親族が来て、「あなたのせいで、あの子までおかしくなった!」と言われたこともある。
「みんなが健康に暮らす、ということを願って始めたことなのに、なんでここまで言われなくちゃいけないのか」と思ったこともある。
しかし、日が昇ってから、日付が変わるまで、農業に没頭しているうちに、周りの目も変わってきた。不信な目で見ていた近所の人も「いいものを作るために一生懸命なただの農業バカじゃないか」と、応援者へ変わっていった。
久保田さん自身も、有機農業というものをオープンなものにしようと取り組んだ。他との関係を絶つ仙人のようになってはいけない。出来るだけ、行政や消費者などとの関わりを持つ様にした。
その結果、県の優良事例にも選ばれ、現在は農業アドバイザーとしても活躍している。
テーマパーク集落で地域再生を目指す
中条では、過疎化が進んでおり、若い人はほとんどいない。このままでは、「豊かな里山風景も荒れてしまう」と久保田さんは危惧する。
「この自然豊かな村を、集落テーマパークのようなものに出来たら最高だよね」と今後の目標を語る。テーマパークと言っても、入場料がかかるようなものではない。中条にいる農家さんやI・Uターンの若い人が協力して、地域全体で農や食、里山風景、宿泊などを楽しめるテーマパーク集落を目指している。
レストランやカフェをやりたい人や焼物、木工など、それぞれがやりたいことを地域全体でバックアップして、それぞれが連携する。そんな地域を想像する。
「この豊かな里山風景が残っているうちに取り組んでいきたい」と熱い思いを語る。地域が有機的な繋がりの中で手を取り合って行く事が、地域再生の鍵を握る。
久保田さんの元で研修を終え新規就農した人は10人を超えた。久保田さんのような考え方が全国に広がる事で、地域の歩みが面白くなっていきそうだ。
有限会社まごころ・ふれあい農園
〒381-3204
長野県上水内郡中条村御山里8338
TEL026-268-3564
fax026-227-0493
HP: http:/www.avis.ne.jp/~magokoro/
(平成26.4.11 産直コペルvol.5より)