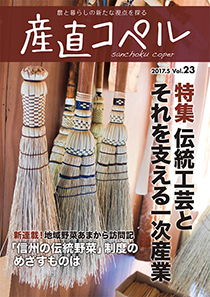全国の地域おこしの先進事例が満載 ―産直コペルより―
農家を訪ねて vol.4 雪と農家がつくりあげるおいしい野菜
冬になると雪が数メートル積もる豪雪地帯新潟県上越市。辺りは一面銀世界になる。そんな中、上越市の直売所「旬彩交流館あるるん畑」(JAえちご上越)には、地物野菜が所狭しと並んでいる。
先人の知恵、雪下野菜だ。雪が積もった畑は真っ白で何もないように見えるが雪の下には沢山の野菜が保存されているのだ。この地で、夏場は稲作、冬場には雪下野菜の栽培に力を入れている山岸マサ子さん(65)。山岸さんは、2012年度からあるるん畑の組合長を務めており、店頭に立って率先して販売を行なっている。上越で生まれ、上越で育ち、上越で40年間専業農家をしている山岸さんを訪ねた。
雪の下で甘くなる
「雪の中は、およそ0℃で安定していて、野菜が凍って死んでしまわないようになっているのよ。野菜自身も寒さから身を守るために糖を出して凍らない様にする。だから甘くて美味しい野菜になるの」と山岸マサ子さんは話す。
雪の多い上越市では、冬場は農業が出来ないというイメージ強かった。しかし、その雪の多さを逆に利用したのがこの「雪下野菜」だ。
雪下野菜とは、夏、秋に植えて栽培した野菜を雪が降ってもそのままの状態にし、雪下で生育させる野菜等のことだ。雪の頃に収穫して雪の下に寝かせておくものもある。 積雪が多い地域の農家は、昔から冬の保存食として自家用に少しずつ作っていた。山岸さんもその1人だ。
この雪下野菜をブランド化して、広く売り出そうと考えたのが、「旬彩交流館あるるん畑」。同店では、「雪下畑の仲間たち」という名前のコーナーを作り、甘くて美味しい雪下野菜のPRに力を入れている。現在は約70名の生産者が雪下野菜作りに取り組んでいる。一昨年7月には、商標登録も取得した。現在、雪下畑の仲間たちとして販売されているのは、ネギ、大根、人参、キャベツ、白菜の5品目だ。
山岸さんも自家用のみだったものを、あるるん畑用に栽培面積を増やして取り組んでいる。
「収穫は本当に大変。普通のものの2倍、3倍の労力が掛かる。それでもお客さんが美味しいと喜んでくれるから頑張れるのよね」と笑顔で話す。
雪が降る中での収穫
雪下野菜の栽培は難しく、苦労も多い。まずは、植え付けの時期だ。雪が降る前に野菜が成熟してしまうと、雪にあたる事で、全体が痛んでしまう。逆にまだ若いうちに雪に当たってしまっても小さいままで生育が止まってしまうため、播種には長年の経験が必要だ。
「雪の時期に合わせて作るのが難しいね。早く雪が降って欲しい!と思う年もあれば、もうちょっと待って!というときもあるのよ」と山岸さん。
栽培がうまくいったら、次は収穫だ。降り積もる雪を手やシャベル、時には1度除雪機などで雪をどけて、野菜を収穫する。寒い中での大変な作業だ。
一見すると畑は、真っ白で、素人が見れば、どこに何が植わっているか分からない。しかし、山岸さんは「この列はキャベツで、こっちに白菜があるわね」と雪の中を進んでいく。何の印もない雪を掘ると中から、キャベツが出てきた。外側の葉は少し痛んでしまうが、外の葉を剝ぐと、きれいなキャベツだ。
しかし、何でも雪の下に入れておけば美味しくなるという訳でもない。しっかりと栽培や管理に力を入れているからこそ、美味しい雪下野菜が出来る。山岸さんは、なるべく有機質の肥料をつかい、農薬を減らした栽培を心がけている。
「雪下野菜は苦労も多いけど、甘味が強くて本当に美味しい。だからサラダなど素材の味を生かした食べ方をして欲しい」と話す。
こうした大変な中でも頑張れるのは、直売所の生産者や消費者との繋がりが大きい。あるるん畑に雪下野菜が沢山並んでいると、「あの人、こんな雪なのに頑張っているな、自分も頑張ろう!」と思える。イベントの販売スタッフとして店頭にいると、消費者から「こないだ山岸さんの野菜買ったわよ。美味しかった、ありがとう」と言われる事もある。こうした喜びや繋がりが生き甲斐になる。
「対面での販売はとても大切なこと。自分が作った農産物に自信が持てるし、良い物を作らなきゃと思えるんですよ」。組合長になって、そのことを強く感じる事が出来る様になった。
雪とうまく付き合う
「雪が多いここでの暮らしは大変。でもね、この土地の四季が体に染み付いて、ここでの暮らしに体が慣れている。それにこの土地の四季はとてもはっきりしていて美しいの」と話す。
冬場に数日間都心などへ出掛けると、雪がない生活というのは楽でいいな、と思う事もある。それでもやはり「雪が降らないと落ち着かないのよね」と笑う。雪が降ると冬が来たと感じ、雪が溶けると春が来たと感じる。1年という四季を体で感じてメリハリを持つ事が出来る。
冬の間は、少し休憩して、春からまた頑張るというサイクルが出来上がっている。「でも雪下野菜を一生懸命作る様になってからは、冬場も忙しいわね」と嬉しそうに話す。
山岸さんはの目標は「一生涯農家」だ。「一日でも長く農業を続けられる様に健康で長生きしたい。雪下野菜の美味しさを広めて、下の世代にも広がっていって欲しい」と語ってくれた。
「雪国だから冬場は農業が出来ない」というところは多いが、雪国だからこそ、出来る事もある。地域に眠っている昔からの知恵や技術を生かす事で、大きなエネルギーを使わずに農産物を生産することは可能だ。
それぞれの地域や場所で条件は異なるが、直売所の冬の売り場作りや農家の冬場の収入源は、もしかしたら身近なところに眠っているかもしれない。
雪下野菜の取り組み
新潟県の人気直売所「旬彩交流館あるるん畑」では、冬場の売り場対策として雪下野菜の販売に力を入れている。
「冬場だから何もない、と考えるのではなく、身の回りにあるものを探して、農家さんに作ってもらい、それをしっかりと力を入れて、販売することが重要ですね」とJAえちご上越の営農生活部園芸畜産課長の岩崎健二課長は話す。
直売所が本気になることで、農家もそれに応えてくれる。農家さんと一緒になって直売所作りをすることが重要だ。
雪国米どころの直売挑戦
JAえちご上越は売上げの9割以上が米という稲作地帯だ。もともと、12月から3月までは、完全に雪で閉ざされてしまうため、園芸に取り組みにくい地域だった。そこに売り場面積80坪の大型直売所「あるるん畑」が平成18年に完成した。
オープンしてすぐは、売上げも順調だったが、米どころで、園芸作物が少なく、野菜の出荷量が伸び悩み、徐々に売り上げは落ち込み始めた。売上げが落ちると、農家も農産物を出荷しなくなる。物がなければ、お客さんが来ても帰ってしまう。この悪循環を断ち切るために、岩崎さんは、農家さんに何かないかと電話を続ける日々を送った。定期的にイベントを打ち、「必ず売るから出荷して欲しい」とお願いして回った。イベントでの売り上げ増を契機に、少しずつものが集まる様になり、お客さんも集まるという、好循環が出来上がってきた。
しかし、問題はやはり冬の売り場だ。雪に閉ざされた地域で冬場のものをどう集めるかが最大の課題だった。そこで、地域の資源を見直していたところ、上越は、雪下野菜が実は豊富な地域だということに気付いた。そこで、雪下野菜の保存方法や栽培指導、品種の選定という講習会を2年程続けた。このときも色んな農家さんに絶対に売るから作って欲しいとお願いして回った。
そして、「雪下畑の仲間たち」というコーナーを作り販売を始めた。雪下野菜は、味の良さからたちまち冬場の売れ筋商品になった。当初は150万円程だった雪下野菜の売上げも今では、600万円程に上がってきている。
「農家さんの手取りを増やして、やる気になってもらう。それが自分の仕事だと思っていますから」と岩崎さんは話す。
現在は、更に美味しい雪下野菜栽培のために種苗会社と連携して、試験にも取り組んでいる。また、全国へ自慢の野菜を販売する計画も進行している。
「地域と組合員に必要とされるJAを目指したい」と岩崎さんは力を込めた。
旬彩交流館あるるん畑
営業時間 AM10:00~PM19:00(4月〜10月)
AM10:00〜PM18:00(11月〜3月)
年中無休(年末年始は休みます)
〒943-0172 新潟県上越市大道福田615
TEL 025-525-1183(いいやさい)
FAX 025-525-1255
(平成26.3.18 産直コペルvol.4より)