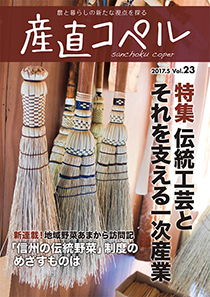全国の地域おこしの先進事例が満載 ―産直コペルより―
目指すのは「売上げ増」ではなく「売残りゼロ」 ―すべては農家のために―
愛媛県 さいさいきて屋に学ぶ
愛媛県のJAおちいまばりが運営する複合型直売施設さいさいきて屋は、全国の直売・6次産業化事業の新局面を切り拓いた、まごうことなき、〝業界〟のトップランナーだ。
直売所、カフェ、食堂、ショップ、各種加工所に加え、実証農園や体験農園など、広く展開されている事業領域。売り場面積2千220平方メートル(約662坪)、延床面積3千597平方メートル(約1千82坪)、実証農園などを含めた総敷地面積が約2万5千500平方メートル(約7千730坪)という巨大な規模。そして、集荷者数約1千180人(団体)、年間来客数120万人、売上げ総額約26億円というビッグな事業実績―どれを取っても国内屈指のものだ。
さらに、新事業・新商品開発でも常に話題を提供しており、全国各地の直売所が―JA系・非JA系を問わず―頻繁に視察・研修に訪れ、そのノウハウを学びとろうとしている。
このような、さいさいきて屋の事業の特徴とその目指すものはどこにあるのか?全国各地の直売所は、あるいはそれをサポートする行政マンや関係者は、いったい何を学び取るべきなのか?―同店を統括する西坂文秀さん(JAおちいまばり直販開発室長)に聞いた。
回りきれない農と食のワンダーランド
「今治のものを売る」直売所
圧倒的な販売力・集荷力
「まず店の中をぐるっと見ますか。なんでも見せちゃいますよ」。出迎えてくれた西坂さんは、笑ってそう言うと、つかつかと店内視察を先導してくれた。
7月末、地場産農産物の出盛り期を迎えた同店は、野菜や果実が、まさに山のように陳列されていた。農産物コーナーだけでも、平台(平面の陳列棚)が10本ずつ集まった〝島〟が、合計20ほど並ぶ。その様は壮観だ。
「葉菜類と果菜類が売上トップで年間約1億5千万円ずつ。根菜類、中晩柑類、落葉果樹類、それに米麦類が1億円から9千万円ぐらいで、売上額で第二グループを形成しています」と西坂さん。あとで見るように、このほか今治産の加工品が3億5千万円、精肉が2億8千万円、地域の漁業協同組合が共同で売る鮮魚が2億7千万円ほどあり、この売上げ額を支える農産物・海産物・加工品が所狭しと並ぶ様子は、農と食のワンダーランドとでも表現するほかはない。
「出荷会員の多くは兼業農家。定年リタイア就農者や意欲ある若手などもいますが、ほとんどは高齢者や女性で、そういう農家の努力でこれだけの農産物を並べさせてもらっていることは、ちょっと胸を張りたいところです」と話した。
ちなみに、店と壁ひとつ隔てたバックヤードに大型精米器1台を設置し、ほぼフル稼働で販売している地元米は、30キログラム袋で年間約2万袋(店売り、ホテル、飲食店、個別配送等含む)。JAおちいまばりの米の取扱量約4万袋の半量に及ぶのだそうだ。
特色ある精肉・鮮魚・今治産加工品
生鮮の農産物の品目と量が圧倒的に多いだけではない。農産物直売所ではあまり見かけない対面販売の精肉コーナーもある。今治に一軒だけの養豚農家・菊間仙高牧場のブランド豚「仙高ポーク」もこの店だけで限定販売されている。本年度の日本農業賞で大賞を受賞した逸品だ。
鮮魚も、大型スーパーの鮮魚コーナーを超える規模の広い売り場で販売されている。JAおちいまばり管内の、島嶼部を含めて14の漁業協同組合が、共同して販売会社をつくり、「獲れたて新鮮」の海産物を港から直送して、ここで販売している。開店時には、野菜と共に、この鮮魚コーナー目当てに行列ができるそうだ。
加工品の品揃えも並大抵のものではない。瓶詰や真空パックなどの保存系から、乾物・せんべい・菓子の系列、弁当や総菜、豆腐や漬物などの日持ちの短いものまで、様々な地元産素材を使った加工品が並ぶ。その中でも、地元今治の農家や、食堂、食品加工会社とコラボレートして製造され、さいさいきて屋のオリジナル商品として販売されている特選加工品が目をひく。「彩菜」と記されたロゴマークが貼られている。
「今治産の原材料を使った、農商工連携や6産業化による商品開発の役に立つことは、地域農業の振興に直結することなので、積極的に提案もするし、相談にも乗ることにしています」という。
圧倒的な集客力と販売力を誇る同店ならばこそ、新商品のテストマーケティングにも向いており、商品開発からヒット商品の創製へ、多くの人々がチャレンジできる条件が整っているのが強みだ。
素材を活かす彩采食堂カフェ・ショップ
もちろん、店で扱う旬の食材を活かした食堂・レストラン事業も展開している。一つは130席の広いフロアーを持つ彩菜食堂で、地元産の素材にこだわった昔ながらの農家の惣菜から、現代風のちょっとおしゃれな一品まで、セルフサービスのカジュアルなスタイルで、昼夜ともに営業している。年間で約1億5千400万円を売上げる、これもビックな食堂事業である。
彩菜食堂とならんで地元客・遠来客の双方に人気なのが、SAISAICAFE。農産物が持つ力を最大限引き出すことを目指して、パティスリー・ベーカリー・ジェラート・ソフトクリーム・生ジュース・フラワー・グリーンなど、多くの工房と60席の広々とした客席を持つ。中でも、出荷される果実をふんだんに使ったケーキやタルト、ジェラードなどのスイーツは、女性を中心に幾多のリピーターを獲得している。著名なパティシエ、鎧塚俊彦氏の協力もあり、年々、評判が高まっているとのこと。
このスイーツづくりに関しては、パティシエなど、あらかじめ技術のあるスタッフを採用するのではなく、さいさいきて屋で働くことになった人が、現場で技術を身に付けていく形にしていることが特徴。西坂さん自身も、ここで技術を習得し、パティシエの資格をとったというから驚きだ。「SAISAICAFEはスイーツを売っているのではありません。直売所に出荷されるフルーツをたくさん売るために、スイーツという形にしているのです。フルーツを売るのだという本来の目的がはっきりしている人は、皆、すぐに上手に作れるようになります」と西坂さんは話す。
また、今治産を中心に季節の花やグリーンが並ぶ花屋のコーナーや、有機無農薬の商品を取りそろえたオーガニックのショップもある。オーガニックのショップには、有機農産物使用・無添加のドレッシングやビネガーなどが並ぶほか、今治の伝統産業であるタオル製造業と連携して、さいさいきて屋自前の有機圃場で栽培したコットンを使った国産オーガニックコットンのタオルなどもあり、新たなライフスタイルを求める比較的若い年齢層の客が着実にふえているそうだ。
ここでも、加工食品のところで触れたさいさいきて屋を拠点にした農商工連携の構築という発想が生かされている。
給食への食材提供とクッキングスタジオ
さいさいきて屋が展開する事業は、そもそも同店の加工事業の出発点となったペースト・ジャム製造や、その発展としての乾燥パウダー製造など、まだまだ多岐にわたり、ここですべて紹介することは、紙幅の関係上、到底不可能である。しかし、同店が進める食育関連事業のことは紹介しておく必要があるだろう。
その主要な柱は、何と言っても、島嶼部を含めて20ヵ所の調理場で44の学校に地元食材を届ける学校給食事業である。食数にして1万4千170食にも及ぶ。直売所を包み込む大きな賑わいに目を奪われがちだが、地産地消の根幹に据えられる学校給食への食材提供においても、確固たる実績を築き上げていることを見落としてはならないだろう。離島の、児童が10名足らずしかいない学校へも食材を確実に届け続けていること。このことが、同店に対する地域住民の信頼感の基礎を形作っている。また、幼稚園の「食農・食育」給食支援や幼稚園給食へもつながっている。
食育のもう一つの柱は、店に設置されたオール電化のキッチンを使用したクッキングスタジオだ。これは食によるコミュニケーションや遊び・楽しみの場を提供することを目指したもので、子どもたちに今治の食文化を伝えていくステージである。大変好評で、週末は毎週、クッキングスタジオの公開講習会が開かれるほか、ウィークデイは、学校や子供会単位での特別コースで埋まっているそうだ。
兼業農家を育てることが第一歩
―大型農家育成一辺倒への疑問
直売所と共に発展する地域農業
以上、さいさいきて屋が展開する複合的直売事業の全体像を簡単にスケッチした。こうしためざましいばかりの事業展開に衝撃を受け、多くのJA系・非JA系の直売所が同地に視察研修に赴き、そのノウハウを学ぼうとしているわけだが、こうした〝現象面〟に着目するのみならず、それを生み出した原動力にまで迫る必要があるだろう。
さいさいきて屋は、いまでこそ日本でも有数の直売所に挙げられるが、スタート時の2000年には、わずか30坪の店舗で、西坂さんを含めてたった3人のスタッフで、直売事業を始めたのだった。当たり前のことだが、最初から複合化した大型店舗でスタートしたのではないのである。
「農協の営農販売を担当していた20数年間、農家が農協からどんどん離れていくのに直面して、大型農家重視の農協の方針、国の方針で良いのかと思ったのが始まりです」と西坂さんは振り返る。大型農家は減少し、農協離れも急速に進んでいた。これに比して、女性や高齢者を主要な働き手とする兼業農家は多数存在し、かつ、栽培方法の指導など、様々な支援・援助を望んでいた。「地域農業を守るためにはきちんとした兼業農家を育成することこそが重要ではないのか!」。その拠点として直売所を開設し、運営することを思いついたのだという。
スタート2年で100坪に店を拡大、トントン拍子に売上げは伸び、7年後の2007年には現在の複合型大型店へと生まれ変わった。
「スタート時の組合員は90人。平均すれば、年間売上げが50万円いくかいかないかという弱小兼業農家ばかりでした。それが現在は会員数で約1千200人まで増え、平均売上げも約81万円になってきた。兼業農家を増やし、その手取り収入を上げることで地域農業を守る。この大目的はまがりなりにも実現してきているという自負はあります」と胸を張る。
農の強化のための新技術・新品種実証農園
こうした、兼業農家の育成で地域農業を強化するという西坂さんの考えを具現化したものが、さいさいきて屋の店舗背後に広がる新品種・新技術実証農園であり、初級・中級・上級の貸し農園である。
519坪の実証農園では、新しい生産技術の実証試験や、新品種などの生産技術の指導、そのための営農指導員の研修などが継続的に行われている。これらはまさに、女性や高齢者、さらには定年リタイア就農者などを対象にして、多品種少量生産の直売所型農業を習得してもらうために行われていることである。この実証農園を舞台にして開発・実証され、またここから伝播普及された農業技術が、さいさいきて屋の出荷組合員の技術を引き上げ、生産力の増大・出荷組合員の拡大につながったことは間違いない。
また、初級から上級までに区分された貸し農園も、初級向けは市民の農への触れ合いの場づくりのものとして位置づけられ、中級・上級は、施設園芸の技術を体得しようとする兼業の出荷組合員を対象にした研修農園として活用されている。特に後者は、本年からイチゴ農家の高齢化が進み、生産力が低下していることの打開策として、直売所としてイチゴの水耕栽培技術を実証研究し、次年度以降、それを普及する予定だという。これらも、農家の拡大と技術向上を目指して進められていることは明らかだ。
カギを握る直売所営農指導員
直売所や実証農園を舞台にした兼業農家の育成指導について、西坂さんは以下のような経験談を教えてくれた。
現在のさいさいきて屋の店舗がスタートしたちょうどそのころ、以前は14あった各地の農協が合併してJAおちいまばりが誕生したのだが、広域合併で以前より農家の顔や腕前を知る機会が少なくなった営農指導員に、朝の出荷時間にさいさいきて屋のヤードに詰めて、出荷してきた農家に声をかけ、情報交換と農家の現状掌握、営農指導員の顔の売り込みをすることを提案したそうだ。
賛否両論あったが、JAおちいまばり組合長のお墨付きもあり、実施することになった。これにより営農指導員と農家の関係が一歩深くなった地区は、明らかにその後の農業生産が好転したという。
残留農薬分析室で「安全・安心」を徹底
もう一つ、さいさいきて屋で農家の技術向上・意識向上の点から位置づけられ、実施されている定期的な残留農薬検査についても触れておこう。これは、全国的にも珍しい直売所に設置された残留農薬分析室で、さいさいきて屋自身の手で検査が行われている。
もちろん直接的には、消費者に対して、店で販売する農産物の安全性を、エビデンス(証拠)を持って証明することを目指している。
しかし、それと同時に、農家自身の農薬使用や環境汚染についての関心を高め、環境保全型農業に移行する意欲を高めるきっかけとなることを目指して、敢えて分析室を自前で設置し、客や農家の眼の前で検査を実施しているのだ。
さいさいきて屋では、生産履歴の記載と管理を全農家に呼び掛けているが、店への提出の義務付けやその点検を行っているわけではない。真実を記載し、自分の農業を改善するのは結局のところ農家自身の努力が重要で、そのためにはややもすれば機械的に行われる危険性もある履歴の記載と提出義務よりも、結果において成分明確に提示される残留農薬検査を採用した。農家には、この検査結果をきちんと説明できるようにトレーサビリティの管理を促しているのだという。
これも、農家の成長に重きを置く西坂さんならではの発想だと言えよう。
ノウハウ移植ではなく、過程の追体験を
繰り返し言うが、さいさいきて屋を、自分の地域で新設する複合型直売所施設のモデルにしようとしている人々は多い。しかし果たして兼業農家育成を中軸にした地域農業の活性化の拠点として直売所を作るというその目的や、そのために実証農園を併設し、出荷農家や営農指導員自身の技術力の底上げをはかるという具体的方策までしっかりと踏襲して実行している地域はどれだけあるのだろうか?実証農園などを併設しても、結局のところ、単に誘客のための交流体験施設として位置づけられているように見受けられるところも多い。
要するに、さいさいきて屋がどのようにして今日の形に立ち至ったかを追体験的に血肉化するのではなく、出来上った結果を「ノウハウ」として借用するというところにそのままとどまっている場合が多いように思われるのだ。
農家への熱い思い、地域へのこだわり
「直売所を始めた当初、当時80歳を超えていた耕作面積が5aほどの農家のおばあちゃんが、売上げ2万円が振り込まれた通帳を持って来て、『わたしが作った野菜が人様に買ってもらえた。こんなうれしいことはない』と涙をボロボロこぼしたことがありました。僕は、その時、かなり驚きながら、この仕事は一生をかけてやる意義があると思ったのです」と西坂さんは話す。
中山間地の高齢化する小さな農業をどうにかして守りたい。農家の手取り.収入を増やしてあげたい。そんな気持ちは年々強くなり、その後も、出荷困難地からの集荷システムの構築などにもつながっていっている。現在では、タブレット端末を使ったネット通販と集荷事業・さらには安否確認を含めた集落維持システムの構築から普及へと取組みを展開させてもいる。それらの原点は、直売所に農産物を出荷し、それが売れたことで初めて自己存在の社会的意義に気付いた、働くことの・生きていることの楽しさに気付いた、小さな農家に対する優しいまなざしと熱い思いなのだろう。
西坂さんは言う。「直売所が目指すべきは売上げ増ではなく、売残りを限りなくゼロにすることです。それが農家や農業を強くする。農業や農業の意義を学び教える原動力になるのです」―と。
日本有数の複合型大型直売所には、農家のことを思うヒューマンな思いが満ち溢れている。
直販開発室室長さいさいグループ代表 西坂 文秀さん
年間売上26億円を誇る直売所「さいさいきて屋」の代表。施設の開設・運営や多様な消費者との交流活動の中心的な役割を担っている。同店は、直売部門だけでなく、農家レストラン・カフェ・市民農園・学童農園などを併設した巨大複合型施設で、どの流域においても、優れた取組みを展開している。
例えば、JAの営農指導員を「直販物生産アドバイザー」として常駐させ、消費者の需要動向を的確に把握。消費者ニーズを栽培に結びつけるための生産誘導に尽力している。
(平成26.8.10 産直コペルvol.7より)