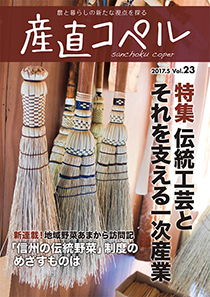全国の地域おこしの先進事例が満載 ―産直コペルより―
直売所列伝 vol.3 直売農業で山間地集落を守れ ―自然の一体として農に生きる―
紫波ふる里センター(岩手県紫波町) 前組合長 堀切 眞也さん(75歳)に聞く
岩手県の内陸部と沿岸部をつなぐ国道396号の沿線。紫波町の山間部・佐比内地区にある峠の駅「紫波ふる里センター」は、本年創立20周年を迎えた東北屈指の「産直」だ(※1)。
岩手県内で最初に産声を上げたこの店を、立ち上げから先頭で牽引してきたのが堀切眞也さん。20年間組合長を務め、20周年を期に後進に道を譲った。
発足当時約430戸だった佐比内集落で、約100人の生産者組合を組織し、果樹を中心とした産直・直売農業の地に育て上げてきた。その産直にかける思いを聞いた。
(※1東北地方では直売所を「産直」と呼ぶ風習が根強い)
「一揆一遊」―直売所が集落を守った
「一揆一遊」―紫波ふる里センターの20周年誌の表紙に記された4文字だ。「一揆」とは、言わずもがな、飢饉などで困窮した農民が悪政に命をかけて立ち向かった「百姓一揆」で有名な言葉だが、その本来の意味は、道や方法、心を同じくして、まとまること、一致団結の意味であるという(広辞苑・岩波書店刊、参照)。
「やる時は、一つにまとまって徹底してやる。一息ついて遊ぶ時には、しっかり遊ぶということだよ。そうやってここまで来た。そんな気持ちを込めたんだ」。堀切さんは、目を細めてそう語った。
堀切さんによれば現在170カ所ほどある岩手県内の常設直売所のうち、最初に産声を上げたのが紫波ふる里センターだという。
ことの発端は、初和の終わり、改修により国道396号の交通量が一挙に増大する中、隣町との町堺に開設された交通安全休憩施設と公園に、思いがけないほどの人が立ち寄るようになったこと。「何かに活かせないか」「産直はどうだろう」…住民の期待は膨らみ、話は「勝手にどんどん発展した」(同センター20周年誌より)。だが、実際にプレハブ店舗で仮オープンする1993年までは、様々な紆余曲折があり、7年ほどの歳月が必要だったそうだ。
「目的は地域づくり。この地域の農業を元気にするために、この地域で自分が栽培したものを売ろうという発想だった。地域農業の維持というよりも、地域そのものを維持するために、皆で力を合わせることが必要だった」と振り返る。
開設から20年。地域づくりの拠点として紫波ふる里センターを運営してきた成果、手ごたえをどこに感じているか―こう問うと、
「組合員の数は、ほぼ100人で継続されている。この10年間の間に亡くなった組合員は10人いるが、どの家でも農業を続けている。この産直センターがあったから、この地域が守られてきたのだ」と堀切さんは胸を貼った。
売上げ1億9千万円でも、レジは当番
現在の売上げ額は約1億9200万円(2012年)。設立以来力を入れているリンゴ・ブドウ・モモなどの果樹を中心に、普段使いの野菜、山菜・ニンニク・山野草などが主力商品だ。ある程度の量、まとまって出荷してもらい、物量感を持たせることが品揃え・棚づくりの秘訣だという。特に果樹のシーズンには、店内からはみ出して軒先に大量の果物が並ぶのが、地域の風物詩になっている。
農産物の仕入れは禁止。「地域農業の振興を目的に設置したのだから、仕入れに頼ったら知恵を出せなくなる」というのが持論だ。厳冬の岩手県、冬場は品揃えに苦労が絶えないが、組合員がそれぞれ保管している野菜を持ちより、「結構、たくさんの種類の品が並ぶ。保存の方法や調理法など、農家には多くの知恵がある」。
現在正組合員は、佐比内地区在住の99人、准組合員が2人。正組合員には出荷番号が付与され、正組合員の同居家族はそれぞれの名前ごとの支払いを受けられる枝番号で出荷することができる。「後継者対策で考えた。親と一緒に住んでいれば新加盟のための出資金はいらない。しかし、自分で育てた農産物の代金は自分の口座に入れて欲しいもの。それで枝番号を付けることにした」という。
しかも、驚くべきことに、販売額が2億円近くになっているにもかかわらず、この産直は、今も、レジスターなどを扱い、お客さんの対応をする販売員は、組合員の当番制。店の職員として店長(日替わりで3人の店長がローテーションで担っている)と、0・5人の事務担当がいるほかは、その日の状況によって1人~8人の当番店員(組合員)によって、店が運営されているのだ。
「別に当番じゃなくても、いつでも農産物を持ってきて、自分で売り子になって売ったって構わない。消費者と対面でものを売り、自分の作ったものの反響を直接肌身で知らなければ、農家は本当の意味で働き甲斐を感じることはできない。それができることが産直の良い所だと考えて始めたのだから、それは守らなければ」と堀切さん。
店内は、当番店員の農家が大きな声で商品を紹介していたり、顔見知りの農家とにこやかにあいさつを交わしていたり…とても賑やか。皆、当番になって店に出ることを楽しみにしている。中には、自分の代わりに孫に当番をさせたりして、孫にも、直売所の楽しさを教えようとしている人も多い。そのことによって逆に、当番店員の若返りが進み、店の雰囲気が華やかになるというメリットもあるという。
正真正銘、生産者=販売者の直売所
紫波ふる里センターの最大の特徴は、なんといっても、そこが、徹底した農家のための産直、地域の生産者を主人公とした直売所であることだろう。
例えば、農産物の出荷については、出荷時間、出荷場所、出荷量すべて原則自由。販売値段の設定も出荷者に任されており、「売れるには売れる訳、売れないには売れない訳がある。それを見極めること」が重要とされている。品質管理は出荷者が主体になって行い、店長が販売不適と判断した物はヤードに下げられる。さらに、清算は、なんと!バーコード管理で、翌日個人口座に振り込まれる…
農家が自らやる気になり、自らの責任と考えで実行することは、それを積極的に応援する―そんな姿勢がどの領域でも具体化されているといえよう。
出荷者は、販売者・管理者の管理の対象ではなく、文字通り、出荷者が販売者として、管理運営者として、自分たちの責任で直売所の運営に参加し、実際に運営して行く―そんなスタイルとシステムが、紫波ふる里センターには根付いているのだ。
その秘訣について、堀切さんは、「産直の経営・営業方針が、地域づくり・地域活性化の方針そのものであることがカギではないか」と話す。実際、紫波ふる里センターでは「経営フローチャート」と名付けられた図解があり、そこには「地域づくり・地域活性化」を進める「経営・営業指針」として、以下の5点が箇条書きにされている。
一、 常にお客の視点で
二、 食品は命の糧
三、 個性がお客を呼ぶ
四、 自由と競争が魅力を生む
五、 全てに応えよう
これが、直売所の経営・営業指針であると同時に、直売所の活性化を通じて佐比内地区の農業を守り、地域を活性化し、この地域から新しい社会を作り出していこうという強いポリシーに裏打ちされたものであることは明らかだろう。
中山間地の継続可能な農業経営を探って
「中山間地では、今後ますます、産直・直売所を中心とした地域農業以外には継続不可能になって行くのではないか」と堀切さんは話す。紫波ふる里センターの組合員が、確固として自分たちの農業を守ってきたことは既に触れた。他方で、堀切さんの古くからの知り合いだった系統出荷・市場出荷の農家で、農業をやめて行った人は数多くいるという。
「これまでも、系統出荷・市場出荷の農業では、ロットの問題、規格揃え・等級揃えの問題などハードルが多かった。これをクリアするにはある程度の広い面積を耕作しなければいけない。そのために、大型機械を買って借金を抱えて来たのだが、高齢になってとてもやりきれなくなった。少なくとも中山間地では、こういう方向性は100%不可能だろう」という意見だ。
実は、堀切さん自身、かつては肥育牛農家だった。だが、1986年イギリスで初の狂牛病が発生した影響で子牛の価格が暴騰し、自分の経営規模では採算が合わないことが分かって、畜産業を廃業した経験を持つ。農業のグローバル化が進展する中、大型化が困難な中山間地で様々な挑戦をしてみたが、しだいにそれは農業とはかけ離れた投機的な事業になり、世界的なアクシデントなどを要因に、結局採算が取れなくなり泣きの涙を見なければならない。
地元の紫波農業高校を卒業して以来、一貫して地域農業に取り組んできた堀切さんは、このような農業の現実を肌身で感じ、規模の農業ではなく、「良いもの。美味しいものを作り、お客に買いに来てもらえる農業」へと転じる決意を固めた。それがふる里を守ることにもつながるという堅い信念のもとに、紫波ふる里センターの開設から運営へと邁進することになったのだ。
世界には、砂漠で暮らして幸福な人もいる
「魚・ハム・お菓子というような組合員がが求める物は、便宜を図って仕入れて売ることも必要だ。けれども、農産物については、安易に仕入れに頼よってはいけない。それでは地域振興にならない」と堀切さんは話す。
ないものは育てる。工夫して挑戦してみる。その精神で、農作物の柱を作り、直売所で苗を用意するなどして栽培振興に務めてきた。
リンゴのほかにもブドウ・イチゴ・モモ・プラムなどを柱にし、様々な品種が採れるフルーツの里を育ててきた。山野草・山菜・キノコ・ニンニクなども特産品に育て上げてきた。
「佐比内」という地名は、アイヌ語で、「水の少ない砂礫交じりの土地」という意味。もともと農業には不利の土地だった。しかし「世界には、砂漠で暮らして幸福を感じる人々もいる」と堀切さん。農業経済にとっては不利な土地でも、人は経済だけで生きているわけではない。地域を守り、人々と共に生き、自然と同化することが限りない喜びになる。そんな農業を、産直・直売所を拠点にして展開して行くべきだと強調する。
「自然の一体として農業をすれば、それを幸福に感じることができる。自分の生命を支えるために農業をすれば、それが地域や人々のためになり、自然のためにもなる。そういう魅力ある農業をしようという勇気と決断が大切だと思う」。組合長の大任を後進に譲ったとはいえ、まだまだ、若く、熱い炎が胸に燃えているようだった。
堀切眞也さん プロフィール
紫波ふる里センター前組合長
現在は、直売所向けの山野草栽培を行い、センターへ出荷している。直売を始める前は250頭の肥育牛経営。
農協理事や(3期9年)、元紫波町議会議員(3期12年)、岩手中央森林組合理事、紫波町産直連絡協議会長を歴任。平成24年度まで、紫波ふる里センター組合長を務めた。
(平成25.12.20 産直コペルvol.3より)