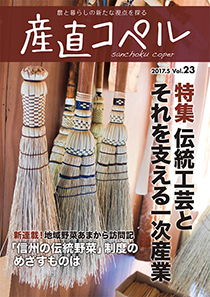全国の地域おこしの先進事例が満載 ―産直コペルより―
島で食べるものは島で作ろう!
離島=南大東島で進む地産地消の取組み
沖縄本島から東へ約400キロの太平洋上に浮ぶ南大東島。開拓以降約110年間に渡りサトウキビの栽培と製糖を中心に成り立ってきたこの島で、近年、地産地消の取組みに力が注がれて始めている。
TPP交渉の状況を睨みながら、基幹産業であるサトウキビ栽培を補完し島の産業構造を複線化する試みの一つとして、地産地消・6次産業化が位置づけられようとしているのだ。人口1200人の離島で、女性を中心に多くの島民の参加で進められる意欲的取組みに焦点をあてた。
野菜の自給率20%の離島
南大東村で地産地消の取組みが強化されたのは、一昨年の同村地産地消促進協議会の発足がきっかけだ。TPP参加の是非が議論の焦点になっていた当時、島の基幹産業であるサトウキビ栽培・製糖を守りながらも、状況の変化に対応しうる産業構造の複線化を図る必要があった。その一つの方法として、島内で消費される生鮮野菜を島内で生産する地産地消を強化することに求めたのである。
南大東村は、戦前は島全部が製糖会社の所有であったことに象徴されるように、徹底したサトウキビ単一栽培の地だ。近年、換金性の高いカボチャなどの栽培・産地化の動きも始まったとはいえ、日常使いの野菜の栽培は、わずかの自家用を除いて、ほとんど皆無に等しい状況が長く続いてきていた。
一昨年末に―産直新聞社もお手伝いして―行った調査では、野菜(青果)の自給率は約20%。各家庭に家庭菜園はあるが、野菜出荷農家はどれも規模が小さく、JAのコープや小売店の直売コーナーに出荷している程度。島全体でわずか7~8軒だった。一方で、島内産の野菜を求める声は、お母さん世代を中心に大きくあり、直売コーナーに並ぶ野菜はすぐに売り切れてしまう状況だった。
こうした状況を突破し、まずは「島で食べる野菜は島で作ろう!」というところから取組みは始まった。
退職者の就労支援と地産地消の合体退
この取組みの先陣役を果たしたのは、意外にも村役場の民生課だった。島内で増加傾向にある退職者(独居が多い)の雇用・健康対策の柱として、夏場の野菜栽培も可能な大規模ハウスを設置し、そこで、本格的に島内消費用の野菜の栽培に取り組むプランを作った(注、同島では盛夏は猛暑でほとんど地場野菜が取れない)。
発案者の一人、同村民生課職員の宮平美智子さんは「退職者が家に篭り何もしないでいると、そのまま寝たきりになってしまうことが多いのです。所得の少ない人も多い。収入面でも健康面でも、退職者が働く場所を作ることが必要でした。それを地産地消の野菜づくりでやってみようと女性を中心に話が進んだのです」と話す。
一昨年夏に結成された同村地産地消促進協議会での研修や議論を経て、このハウスならびに関連施設の役割や体制は次のように具体化された。すなわち―
(1)大規模ハウスを利用して農作業をする「働き隊(=ハルサーエーカ)」を募集し、野菜・花きの栽培をしてもらう。農作業の計画ならびに作業台帳・防除履歴・売上台帳の管理、経費やハルサーエーカへの報酬支払などの業務は嘱託職員を一人置いて、それが行う。
(2)ハウスは島の地産地消をコーディネートし、農家や小売店・飲食店・学校給食などを結ぶ集配荷センターの機能も持つ。イ・個人農家への出荷依頼などの調整、ロ・各商店や社会福祉協議会施設・学校給食センターからの受注やそこへの配送、ハ・農業普及員等とも協力した野菜づくりや堆肥づくりの講習会などを行う。これらは地産地消促進協議会のメンバーがサポートする。
(3)役場民生課と産業課が連携し、主に農作業の調整(高齢者ではできないトラクター利用など)やハウスのハード面(台風時対策や備品関係)は産業課が、働く人々の健康管理などは民生課がサポートする。
―と、いうように。
女性パワーで活発化する野菜栽培
この集配荷センターの機能も持った野菜栽培ハウスは、2013年春に稼働開始。地産地消促進協議会に集まる女性を中心に、島内の多くの人々の協力を得て、順調に事業を拡大しつつある。
同協議会のメンバーは、JA南大東支所の役員や、食品小売店の店長、島内の食品加工団体の代表、役場教育委員会で食育を担当する職員など、村内で地産地消のカギを握る役職・立場の人(ほぼすべて女性)で構成されており、その人たちがハウスの取組みに協力しているだけでなく、ハウスの業務を司る嘱託職員も志を同じくする女性農家が手を挙げ、ハルサーエーカの先頭に立って、農作業を進めている。
こうした「島の食を自分たちの手で変えたい」という思いに満ちた努力の積み重ねが、島の多くの人々を揺り動かし、地産地消の取組みへの協力を促しているのである。
「島の女性たちは、ずっと長い間、子どもたちに島で取れた野菜を食べさせたいと思い、見よう見まねで家庭菜園などもしてきました。でも、とても需要をまかなえませんでした。今度できたハウスが成功して、もっと野菜の栽培が広がれば、生鮮野菜は島外からの移入に依存していた島の食環境が大きく変わると思います」とハウス嘱託職員の川満みどりさんは話す。
栽培技術・土づくりの講習、活発に
野菜栽培ハウスの取組みは、島の農業に新たな動きを生み出している。野菜栽培を、そのための土づくりから根付かせようという試みだ。
南大東村は、サトウキビ単一栽培の地であり、しかも日本でも有数の大型機械作業が導入されている。これまでもバガス(サトウキビの搾りかす)のすき込みや化学農薬の使用規制などを行ってきていたとはいえ、長年にわたり大型機械で踏み固められた大地は、地力が衰えサトウキビの反収も明らかに落ちてきていた。
そのような中で、本誌を介して同島の取組みを知ったNPO法人「土と健康つくり隊」の伊藤勝彦代表らの助言もあり、この野菜栽培ハウスでは、天然肥料を使用した土づくりからの野菜栽培が目指されている。それは、安全安心の地元産野菜を子共たちに食べさせるために、残飯等を持ち寄ってぼかし肥料を作ってきた、島のお母さんたちの粘り強い取組みを発展させるものでもあった。
そして実際、野菜栽培ハウスでの農作物の生育状況が良好なことにより、このハウス以外にも、サトウキビやカボチャの生産農家に、改めて、土づくりに力を入れようという機運が広がり始めているのである。
活発化する加工、食文化の掘り起し
野菜栽培ハウスを中心とした島内産野菜の供給量増大の試み、また、それを小売店や学校給食で利用しやすくするための配送網構築の試みは、手作り加工や、食文化の掘り起し、食育などの領域で新たな活性化も呼び起こしている。
地元産食材の見直しの機運が高まり、近年、注目を集め始めたカボチャをつかった羊羹やまんじゅう、また島に自生する月桃を使ったお菓子などの新商品が開発された。
また、周辺の海域は日本有数の好漁場であるにもかかわらず、輸送手段がないために、島への水揚げが極めて少なかった漁業に関しても、レトルトなどによる加工品開発の取組みなどが活性化している。
そしてこれと軌を一にするかのように、季節ごとの島の食材とその利用法をまとめた「旬の食材カレンダー」作りも進んだ。さらに、それにまとめた島の特産料理で、実際に観光客をもてなすための「大東御膳」プロジェクトも、島商工会婦人部などを中心に進行中である。
まさに、「地産地消」を旗印にして、女性を中心にした多くの島民が、それぞれの立場から地元食材の生産・加工・調理・販売などを複合的に進め、「食と農」による地域振興を進めている。これこそが、「地産地消」の取組みが持つ底力だということができよう。
冒頭にも述べた通り、南大東島は太平洋上にぽっかり浮かぶ島である。海岸線はすべて岸壁で、沖縄を象徴するイメージとさえいえる〝白い砂浜〟は一ヵ所もない。現在でこそ、天候さえよければ一日二便のプロペラ機が那覇空港と南大東空港とを結ぶが、気候の変動は激しく、生活物資は輸送船に頼るしかない。しかし、打ち寄せる波が荒いため輸送船は接岸できず、クレーンで荷物(時には人も)を釣り上げて陸揚げする、まさに絶海の島なのである。
この島で、人々は、たくましく生きてきた。サトウキビを育て、夢と希望を大きく描いて、島の産業と暮らしを作り上げてきた。その島が、TPPをはじめとする農業政策の新たな展開の下で、その存立基盤から大きく揺さぶられている。そして、その新たな苦難を克服するために、島民は「地産地消」を一つの取組みとして選び、今全力でそれを進めつつあるのだ。ぜひ、南大東島を訪ねていただきたい。
(平成26.3.16 産直コペルvol.4より)