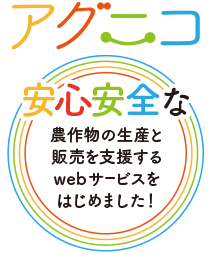直売所がこの先生きる道を共に探る
農産物直売所が農村集落で果たす3つの重要な役割
日本農業、特に中山間地の農業は、急激な農業者の高齢化と減少などを要因にして耕作放棄地の増大に直面し、地域農業だけでなく農村集落そのものの〝消滅〟の危機に瀕しています。ここをどのようにして乗り越えて行けば良いのでしょうか。
農産物直売所がそのための大きな役割を担っています。直売所は、中山間地でどのような役割を担ってきたのか――についてお伝えします。
直売所の一つ目の大きな役割は、何と言っても、そこに住み・農産物を作る人々の農業と収入を守り、元気にしている点です。農村の経済的活性化の源の一つが直売所です。
もとの始まりは、農協に出荷しても扱ってもらえない規格外や少量品目の農産物を自分たちで直接販売して、売上収益につなげたのが直売所でした。実際に直売所で販売してみると、採れたて完熟のおいしい農産物や、規格外や外見が悪くても味に遜色のない農産物が輸送費や各種中間マージンがかからずにお手頃価格で手に入るなどのメリットがあり、消費者に歓迎され、瞬く間に全国各地に広がっていったのです。
特に、農業を進めるには条件が不利な山間地の方が、小規模でも手間暇をかけて多品目の農産物を栽培する直売所型農業が向いていたと言えます。高齢者でも女性でも新規就農者でも、自分の農産物を出荷でき販売できる直売所は農家の現金収入の新しいチャンネルになり、やがて規模の大きな専業農家も積極的に利用するようになってきたのです。
現在の直売所の中には、様々な要因で経営が立ち行かなくなっているところもありますが、その点をうまく克服することはできれば、農村の経済的活性化の源という役割は今も十分果たすことができるはずです。
直売所は上記の経済的役割から派生する、暮らしや生活に関する様々な役割を担ってきました。これが二つ目です。
例えば、直売所では、農産物だけでなく漬物やお餅・おはぎなどに代表されるような手作り加工品も評判が高く、当然、それを作るための加工技術の継承が進みました。食品だけでなくわら細工や木工品などの工芸品も同様です。このような食や暮らしに密着するモノづくりが継承されてきたのも直売所があってこそのことです。
また、こうした農と暮らしを守り継承する取り組みには、人々の協力やグループ化が不可欠であり、畦畔や水路の整備に代表されるような集落共同の仕事を進める連携体や、小規模の加工グループ、さらには年齢や性別などによる人々の寄り合い的集まりを守ってきたのも直売所の重要な役割でした。このような集落の人々のつながりは、今で言えば「相互見守り」「買い物や送り迎えの相互援助」のような機能を知らず知らずのうちに果たしてきたと言えます。集落の景観維持にも役に立ってきたはずです。
農村集落は産業・経済・福祉・暮らしなどの多面的な機能を有していますが、それをまさに現場で支えてきたのが直売所であったと言っても決して過言ではないでしょう。
これまでの述べてきたことと重なることでもありますが、あえて強調したい三つ目のことは、直売所が農村集落の自発的な学びの場であり、情報発信の拠点の場でもあるということです。
直売所という場所は学ぶべき事柄が溢れている場所です。農作物の特徴・食べ方・調理法・保管法・栽培方法はもちろんのこと、それらに係る学問研究の歴史、土地々々の風土や歴史、そこにすまう人々の風俗暮らし、農村や山林を取り囲む環境の変化や時代ごとの農業や農村の在り方に係る施策や政治の変遷など―様々な分野の事柄を相互に学び発信する機会に恵まれた場所であると思います。
「発信する機会に恵まれている」というのは、お客さんへの説明や、同じ直売所の仲間や関係者との意見交換の必要性などが常にあり、出荷農家、運営スタッフ、そして買っていただくお客さんまでもが、好奇心と学ぶ姿勢さえあれば、自ら学び発信する機会が無限大に広がっていると考えるからです。
直売所は発生以来約30年の歴史を経ています(約50年という意見もあります)。その間に全国に広がり売り上げを大きく伸ばし、今や物流チャンネルの一つに数えられていると言えるでしょう。しかし、それと同時に、今見てきたような本来果たしてきた役割をどこかに置き忘れて、ただの「モノを売る場」化が進んでいると言えなくもないのが実情です。ここで改めて直売所が農村集落で果たしてきた、またこれから果たすべき役割をもう一度再確認する必要あるのではないでしょうか?
(産直コペルvol.70 直売所読本 第10回より)
農産物直売所がそのための大きな役割を担っています。直売所は、中山間地でどのような役割を担ってきたのか――についてお伝えします。
その1:中山間地農業を元気にする役割
直売所の一つ目の大きな役割は、何と言っても、そこに住み・農産物を作る人々の農業と収入を守り、元気にしている点です。農村の経済的活性化の源の一つが直売所です。
もとの始まりは、農協に出荷しても扱ってもらえない規格外や少量品目の農産物を自分たちで直接販売して、売上収益につなげたのが直売所でした。実際に直売所で販売してみると、採れたて完熟のおいしい農産物や、規格外や外見が悪くても味に遜色のない農産物が輸送費や各種中間マージンがかからずにお手頃価格で手に入るなどのメリットがあり、消費者に歓迎され、瞬く間に全国各地に広がっていったのです。
特に、農業を進めるには条件が不利な山間地の方が、小規模でも手間暇をかけて多品目の農産物を栽培する直売所型農業が向いていたと言えます。高齢者でも女性でも新規就農者でも、自分の農産物を出荷でき販売できる直売所は農家の現金収入の新しいチャンネルになり、やがて規模の大きな専業農家も積極的に利用するようになってきたのです。
現在の直売所の中には、様々な要因で経営が立ち行かなくなっているところもありますが、その点をうまく克服することはできれば、農村の経済的活性化の源という役割は今も十分果たすことができるはずです。
その2:山間地の生活に必要な多面的で複合的な役割
直売所は上記の経済的役割から派生する、暮らしや生活に関する様々な役割を担ってきました。これが二つ目です。
例えば、直売所では、農産物だけでなく漬物やお餅・おはぎなどに代表されるような手作り加工品も評判が高く、当然、それを作るための加工技術の継承が進みました。食品だけでなくわら細工や木工品などの工芸品も同様です。このような食や暮らしに密着するモノづくりが継承されてきたのも直売所があってこそのことです。
また、こうした農と暮らしを守り継承する取り組みには、人々の協力やグループ化が不可欠であり、畦畔や水路の整備に代表されるような集落共同の仕事を進める連携体や、小規模の加工グループ、さらには年齢や性別などによる人々の寄り合い的集まりを守ってきたのも直売所の重要な役割でした。このような集落の人々のつながりは、今で言えば「相互見守り」「買い物や送り迎えの相互援助」のような機能を知らず知らずのうちに果たしてきたと言えます。集落の景観維持にも役に立ってきたはずです。
農村集落は産業・経済・福祉・暮らしなどの多面的な機能を有していますが、それをまさに現場で支えてきたのが直売所であったと言っても決して過言ではないでしょう。
その3:食・農業・農村・環境などを学び発信する場としての役割
これまでの述べてきたことと重なることでもありますが、あえて強調したい三つ目のことは、直売所が農村集落の自発的な学びの場であり、情報発信の拠点の場でもあるということです。
直売所という場所は学ぶべき事柄が溢れている場所です。農作物の特徴・食べ方・調理法・保管法・栽培方法はもちろんのこと、それらに係る学問研究の歴史、土地々々の風土や歴史、そこにすまう人々の風俗暮らし、農村や山林を取り囲む環境の変化や時代ごとの農業や農村の在り方に係る施策や政治の変遷など―様々な分野の事柄を相互に学び発信する機会に恵まれた場所であると思います。
「発信する機会に恵まれている」というのは、お客さんへの説明や、同じ直売所の仲間や関係者との意見交換の必要性などが常にあり、出荷農家、運営スタッフ、そして買っていただくお客さんまでもが、好奇心と学ぶ姿勢さえあれば、自ら学び発信する機会が無限大に広がっていると考えるからです。
直売所は発生以来約30年の歴史を経ています(約50年という意見もあります)。その間に全国に広がり売り上げを大きく伸ばし、今や物流チャンネルの一つに数えられていると言えるでしょう。しかし、それと同時に、今見てきたような本来果たしてきた役割をどこかに置き忘れて、ただの「モノを売る場」化が進んでいると言えなくもないのが実情です。ここで改めて直売所が農村集落で果たしてきた、またこれから果たすべき役割をもう一度再確認する必要あるのではないでしょうか?
(産直コペルvol.70 直売所読本 第10回より)